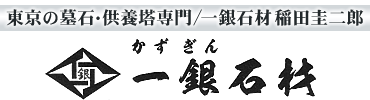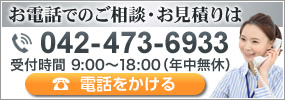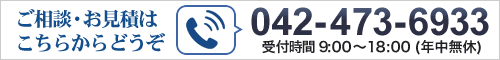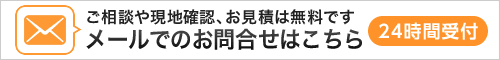江持石の「小たたき仕上げ」をご紹介!仕上がりのようすや方法、使う道具等について解説
東京都一円にて、お墓づくりをはじめ、お墓の様々なご要望にご対応しております、一銀(かずぎん)石材の稲田圭二郎と申します。今回は、江持石の「小たたき仕上げ」についてご紹介いたします!
 【小たたき仕上げ 仕上がりのようす】
【小たたき仕上げ 仕上がりのようす】
「小たたき仕上げ」は、手加工による石の表面仕上げの方法のひとつです。のみ切り仕上げ・ビシャン仕上げなどのさまざまな手加工仕上げの中でも、最も難易度が高い仕上げ方法です。仕上がりの見た目は、よく見るとこのように細かな平行線状の刻み目が付いています。

こちらは江持石の原石です。江持石は福島県で採れる安山岩で、色味の違いから大きく3種類に分けられます。ひとつの作品を製作するために極力色味を合わせたいので、今回は白手のものを厳選しました。
【石の仕上げの種類①小叩き仕上げについて】 1分57秒
こちらの動画では、小叩き仕上げの仕上がりのようすや、小叩き仕上げの方法、使用する道具などについて解説しています。
 両刃
両刃
 片刃
片刃
こちらが小たたき仕上げに使う、「両刃」と「片刃」という道具です。刃の部分は、タンガロイという超合金でできています。動画の中でも解説していますが、今回は両刃で2回叩き、片刃で最終仕上げで締めています。両刃の方が片刃よりも重さがあり、幅が狭いので、より石に食い込みます。江持石や白河石のような中硬石の場合、本来は片刃だけで叩きますが、今回は機械で切ったところをそのまま叩いたので石自体が少し締まっていることもあり、重さのある両刃で叩いてから片刃で仕上げました。

仕上がりのようすです。叩くことで石が締まって硬くなり、表面にはこのように平行線状の細かい刻みがつきます。細かいから良いというわけではなく、角度を一定に入れていくのが重要です。刻みの向きは、棹石などでは縦向き、柱や外柵などでは横向きになります。
小たたき仕上げはこのような筋状の模様を付けることだと思っている人もいるのですが、本来の小たたき仕上げは、細かく叩くことによって石がもともと持っている色や模様を引き出す仕上がりが理想です。

小たたき仕上げでは、石に水を打ってから加工を始めます。中硬石に分類される江持石などの安山岩は、叩くときにカラカラに乾いていると石の表面がめくれて(叩いているところが取れて)しまいます。そのほかにも、叩き目が見やすいように、叩いた時に粉が出にくいようにという理由もあります。
 加工が終わりました。こちらは六地蔵の台座になる部分で、横向きに叩いていることが分かると思います。角の部分は叩いていないように見えるかもしれませんが、実は少しだけ縦方向に叩いています。角をビシッときれいに出すためです。
加工が終わりました。こちらは六地蔵の台座になる部分で、横向きに叩いていることが分かると思います。角の部分は叩いていないように見えるかもしれませんが、実は少しだけ縦方向に叩いています。角をビシッときれいに出すためです。
私自身、技術を師匠から受け継いで職人としてもう30年ほど経ちます。修行時代には、名工と呼ばれる人の作品を必死で探して勉強しました。小たたき仕上げ自体は、鎌倉時代の小松石(神奈川県産)の石塔にも見られます。両刃のようなもので叩いている跡が見られるのですが、これは仕上げとしての小たたきではなく、おそらく表面を平らにするために叩いたもので、現代のように美しい仕上げとしての小たたきになったのは、私は明治以降ではないかと考えています。というのも、修業時代にたくさんの作品を見に行く中で、「どうしてこんなにきれいなんだろう?」と感じたのは、明治以降の名工と呼ばれる人の作品だったからです。大正に入って国会議事堂を作るとき、関西から腕のいい職人がたくさん関東に流れてきたと言われていますので、職人たちが腕を競い合った結果、技術も高まっていったのではないかと思います。
こうした手加工の技術を持ち、すべて完全に手加工で仕上げることができる職人さんも、今ではかなり少なくなっています。次世代を担う若い職人さんに技術を受け継ぐことも大切にしながら、私自身も作品製作に取り組むことで、昔の自分のような次世代の石工を目指す若者たちに技術を残すことができればうれしい限りです。これからも機会があれば、手加工のことについてご紹介してまいります!
こだわりの手加工については、こちらをご覧ください → こだわりの手加工「石工一銀」